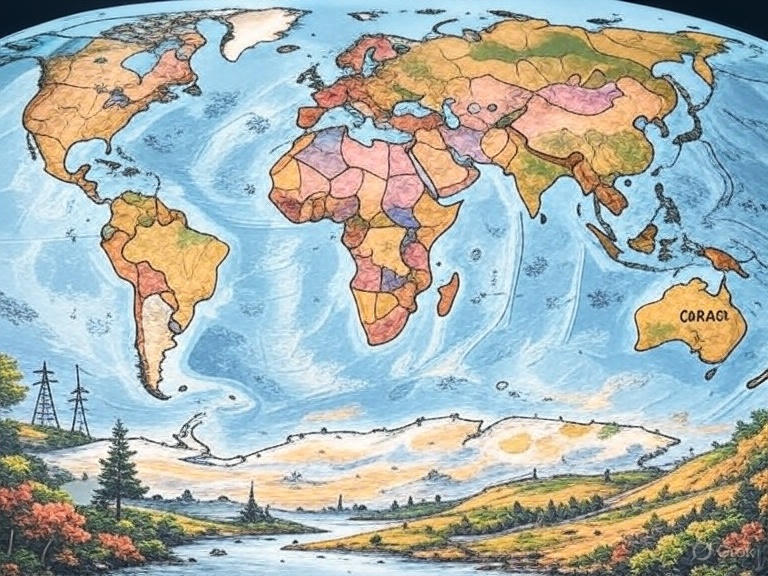今回は、ピーター・ザイハン著の『「世界の終わり」の地政学 野蛮化する経済の悲劇を読む 上』(Amazonで購入)と『下』(Amazonで購入)を読みました。この本は、グローバル化の終わりとそれが引き起こす経済の変化を、地政学の視点から鋭く分析しています。全米で40万部を超えるベストセラーで、日本版も上・下巻で詳しく解説されています。脱グローバル化の衝撃や、エネルギー・資源・食糧の問題がどう世界を変えるかを知りたい人にぴったりです。未来の経済や地政学に興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
#1 本書をなぜ読んだのか?
私は、未来の世界を想像し、準備するためにこの本を読みました。今、世界はウクライナ紛争や中東情勢、気候変動など不安定な要素がいっぱいです。そんな中で、グローバル化が崩壊したらどうなるのか? 日本のような資源依存の国はどう生き残るのか? を知りたくて手に取りました。著者のピーター・ザイハンは地政学の専門家です。この本を読むことで、個人レベルで備えられることや、ビジネスチャンスを探れるんじゃないかと思いました。実際に読んでみて、目からウロコの視点がたくさんありましたよ。
#2 本書の中で特に印象に残った内容は?
この本は、グローバル化の終わりがもたらす「無秩序」の時代を、地政学的に解説しています。上巻では主に歴史的背景と経済の基盤、下巻では具体的な国々の未来像が描かれていて、全体として衝撃的です。特に印象に残ったポイントを、引用を交えて紹介します。これらは、脱グローバル化の現実を突きつけてくる内容ばかりです。
- 日本の経済状況について
日本の経済は行き詰っている。インフレ調整後の数値で見ると、二〇一九年の日本の経済規模は一九九五年より縮小している。自国民による生産にも、自国民による消費にも期待できないとなれば、従来の基準を変える必要がある。
日本が直面する高齢化と経済縮小の問題をストレートに指摘していて、読んでいてドキッとしました。グローバル化に頼ってきた日本が、これからどう変わるべきかを考えさせられます。
- ヨーロッパのエネルギー依存:
ヨーロッパ諸国は、アジア諸国以上にエネルギーを輸入に頼っており、この問題を解決する方法について大国相互の意見が一致していない。
ヨーロッパは諸国では高齢化が進んでおり、理論的に言って人口を増加させられるレベルをずいぶん前に通り過ぎている。
ヨーロッパの弱点を地政学的に分析していて、エネルギー危機がどう連鎖するかがよくわかります。ロシアのウクライナ侵攻を思い浮かべながら読むと、現実味が増します。
- 米ドルの歴史的転換:
一九七〇年代初めにニクソン政権は一連の改革を通じて、金への兌換を打ち切り、米ドルを自由変動相場制へと移行させた。 その結果、主要国のなかで初めて、金庫室に資産を保有しているふりさえしない、驚くべき政府が登場した。ドルを保証する唯一の「資産」は、アメリカ政府の「十分な信頼と信用」だけとなった。
アメリカがどう世界の中心になったかを、金本位制の終わりから説明。グローバル化を支えてきた米ドルの役割が、いずれ終わりを迎える可能性を暗示しています。ただし、米ドル以外の何に分散投資するかは注意が必要です。
二〇二二年時点で、充電式電池で気候問題を乗り越える可能性をほんの少しでも示せるほどのエネルギー密度を持つ物質はコバルトしかない。(中略)商品になりうるコバルトの半分以上は、たった一つの国、コンゴ民主共和国から生産されている。
富との結びつきと褪せない輝きを持つ金は、価値の貯蔵手段や通貨価値の裏付けとして、現代に至るまで愛され続けている。世界大戦開始と米ドルの台頭までは、ほとんどの国が自国の経済システムを支えるために金を保有していた。そして、米ドルが為替取引の中心となった今の時代でさえも、金はほとんどの国において三番目か四番目に多い準備資産である。
資源の地政学的リスクを具体的に挙げていて、EV電池や金のようなものがどう世界を変えるかを学べます。
- 食糧とエネルギーのつながり:
天然ガスは、窒素肥料の製造のほぼすべての面で中心的役割を果たしている。窒素は葉の成長促進に不可欠な栄養素なので、窒素肥料はトウモロコシや小麦などの一年草にも果物や野菜にも重要である(花は「葉」の特殊な形態なのだ)。国内で精製する原油を調達できない国は、窒素肥料を生成できない。
食糧輸出国のランク付けをしてみよう。 食糧輸出国の一つ目のカテゴリーは、資金から肥料、燃料に至るまであらゆるものの供給体制が国内で十分に整備されていて、少し調整すれば現在の食料品群の生産を継続できる国だ。 すべての条件をクリアするのは、地球上でフランス、アメリカ、カナダだけである。
エネルギーと食糧の連動がよくわかる部分。グローバルサプライチェーンの崩壊で、食糧危機が起きやすい国が明確になります。
- 気候変動の地政学的影響:
暖かい空気のほうがより多くの水分を保持できるが、空気が暖かければ雨を降らすために必要な湿度も上がる。湿度の低い地域では、気温が上がると一般的に雨が減るが(オーストラリア)、湿度の高い地域では一般的に雨が多くなる(イリノイ州)。この違いは極端な気候の場所で最も顕著だ。今後ほとんどの砂漠はより暑くなり、より乾燥し、既に乾燥している地帯のほとんどでは砂漠化のリスクが高まる。その一方で、熱帯地方の降雨量増加は平地を湿地に変えるだろう。砂漠と湿地は作物を育てるにはまるで役に立たない。
気候変動が地域ごとの農業にどう影響するかを、地政学的に解説。未来の食糧問題をリアルに感じます。
これらの内容は、著者のデータに基づく予測が基調で、読むと世界の「弱い部分」が見えてきます。他のレビューを見ても、「わかりやすい」「衝撃的」「日本への示唆が多い」との声が多く、私も同意です。
#3 本書はどんな人にお勧めか?
この本をおすすめするのは、以下の3つの読者像です。最大3つに絞りましたが、どれも未来志向の人にぴったりですよ。
- 地政学や経済の未来に興味があるビジネスパーソン:グローバル化の変化がビジネスにどう影響するかを知りたい人に。投資やキャリアのヒントが得られます。
- 日本経済の課題を考える人:高齢化や資源依存の日本が、どう世界の変化に対応すべきかを具体的に学べます。政策や個人レベルの備えを考えている方に。
- 気候変動や資源問題に関心がある一般読者:専門的すぎず、平易に書かれているので、ニュースを深掘りしたい人に最適。脱グローバル化の現実を知って、準備を始めたい人へ。
この本を読んで、私自身も未来の経済リスクを再認識しました。皆さんも、グローバル化崩壊のシナリオを知るために、ぜひ手に取ってみてください。上巻から読みやすいですよ。上巻をAmazonでチェック 下巻をAmazonでチェック